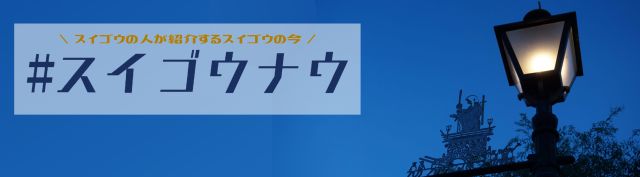浮かぶ港湾ジオラマ「大連港船客待合所」をつくる06
2025/4/19

このところ、本業の年度末・年度初め業務が忙しく、毎日帰宅してはバタンキュー。休日なんてこの2か月は無いも同然の状態だったので、全く記事を更新できませんでしたわ。

ほんでは、行ってみましょうレッツ・メイク大連港♬
前回までの記事で、港湾建築物は大体出来上がってきていますが、港の賑やかしが全くありませんので、その辺作っていきますよ~。
港と言えば、タグボート!昔風に言えば曳船ですな。当時既に、東洋でも屈指の大規模港湾となっていた大連ですから、たくさんの曳船もいたはずです。
で、調べてみたら、大連港の曳船界の顔として「大連丸」という大型のタグがあったそうです。今回は、こいつを作っちゃいますよ~。
画像は『新造船写真史』(三菱重工横浜造船所)より引用
昭和12年に編集された『大連港要覧』という資料によると、当時の大連港には19隻の曳船がおり、その中でも最大のものが「大連丸」だったそうです。
色々調べていくうちに、この船の諸元も以下のように明らかになりました。
「大連丸」諸元
〇排水量:440t
〇全長:41m
〇全幅:9.14m
〇喫水:4.6m
なるほど、1/200にするには程よい大きさですな!
というわけで、小型船を作る時のセオリーとなりつつある紙船工法で起工しました。
発泡スチロールでのコア作り。サクサクッと作っていきます。
船体のコアができたら、いよいよ紙貼りの下準備です。
和紙(半紙みたいなの)を木工ボンド水溶液でヒタヒタと貼り付けて下地を整えます。
で、まずは一層目として、工作用紙を縦方向に巻き付けるようにして貼り付けていきます。
画像は工作用紙の貼り付けが終わり、サラサラ系の瞬間接着剤を塗布して、田宮パテで紙同士の継ぎ目の隙間を埋めた状態です。
船尾の形状が複雑なので、工作がめんどかったです。
紙を小さくして現物合わせでペタペタと貼っていきます。
第二層は、工作用紙を横方向に張り付けていきます。
工作用紙を貼り付ける時、面にぴったりと合うように濡れ雑巾等で湿らせてから貼り付けますが、水分量が多すぎると、このように乾燥した時に大きく収縮して、紙同士の間に隙間ができてしまします。加減が難しいです。
貼り付けが終わったら、一層目同様サラサラ系瞬間接着剤を塗布して、パテ埋めを行います。

完全に乾燥したら、船体のコアをボリボリと抜き取っていきます。
張り子のお面製作と同じ原理ですな。
防水処理として、FRPを表と裏の両面に塗布し、その上から油性のサンディングシーラーを4層くらい厚塗りしていきます。
乾燥したらやすり掛けを行うと、紙製だけど耐水性の船体が完成します。
上部構造物は、主に1㎜厚のボール紙と工作用紙等でちゃちゃっと作ります。
色々細かいパーツをくっつけていくと、それらしくなってきました。
大正期の船らしいゴツいシルエットが魅力的です♡
塗装して完成です。
まずは横から。
斜め前から。
斜め後ろから。特に船尾付近が写った写真が見当たらず、甲板上の機材等は全ておいらの推測です。
大連港の船客待合所から見るとこんな感じ。実際にこのようなアングルで撮られた絵葉書が存在しています。
早く水面に浮いている状態が見たいものであります!
と、そんなわけで、来る令和7年5月24日(土)に、千葉市にある稲毛海浜公園浜の池で、13時ごろから大連港をドーンと浮かべちゃおうと思います。1/200お船系ラジコン好きな方はぜひとも遊びにいらしてくださいな♪
そんでは、また~。