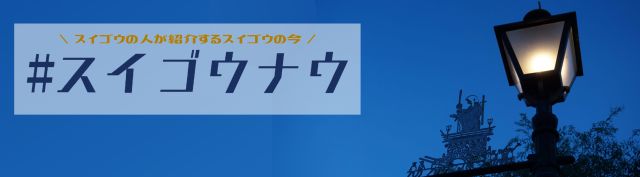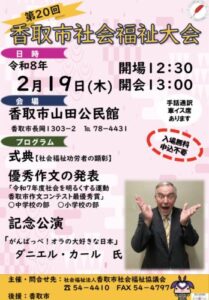第2回:年番引継ぎ行事と町内の誇り
在郷町から生まれた佐原の祭り
佐原の大祭 秋祭りは、城下町の祭礼ではなく在郷町の祭礼として発展しました。
幕府や藩からの支援は一切なく、山車の建造費も運営費も町人たちの自己負担によって続けられてきました。利根川舟運によって江戸との経済的・文化的な交流が盛んになったことで、祭りは町人文化の結晶として発展しました。
初期の祭りは母衣・傘鉾・花万燈などの練物行列が中心でしたが、享保年間(18世紀前半)には山車が登場し、囃子を伴う練物が町の名物に。町並みの整備とともに財力を増した町々は、それぞれに山車を作るようになりましたが、山車を出す順番をめぐって争いが絶えませんでした。
そこで享保6年(1721年)に新宿村名主・伊能権之丞が調停し、山車の番組順を制定。これが現在の年番制度へと発展していきます。
年番制度 ― 9年をかけて守り続ける伝統
年番制度は、祭りの秩序を保つために確立された佐原独自の仕組みです。
**「正年番」「前年番」「後年番」**の三つの役割を各町が順番に務め、3年間をひと回りとし、都合9年をかけて祭り運営に携わることで伝統を脈々とつないできました。
2025年の秋祭りでは、年番が下川岸区から上中宿区へと引き継がれます。年番町は山車の番組順の管理や行事の進行、秩序維持などを担い、町全体の総力を結集して祭りを支えます。
2日目が熱い!山車整列と下川岸巡行
今年の注目は、42年ぶりに下川岸地区で山車の巡行が行われることです。
また、山車整列は2日目(土曜日)に2回行われる特別なスケジュールとなっています。
- 10:40 山車整列(万代橋を先頭)
- 12:10 山車巡行(揃い曳き)
- 15:40 山車整列(入船橋公園を先頭)
山車が一堂に並び、囃子が響き渡る瞬間は迫力満点で、カメラを構える観光客に人気のシーンです。

御旅所と諏訪神社の役割
祭り期間中は、諏訪神社の御神体が町へ渡御されるための「御旅所(おたびしょ)」が設置されます。
この御旅所は諏訪神社から神様が臨時でおりてこられる場所で、2025年はセブンイレブン佐原駅前店の敷地内に設置されます。
山車整列が行われる場所とは別で、神事における重要な拠点です。
山車の構造と見どころ
佐原の山車は、4輪2層構造の「佐原型曳山」です。下層には笛や太鼓を奏でる囃子連(下座連)が座り、上層には歴史上の人物や神話を題材とした大人形が据えられています。
華やかな彫刻や金具が光る山車は、それぞれの町が受け継いできた誇りの結晶です。

初めて訪れる方へのポイント
- **2日目の山車整列(万代橋・入船橋公園)**は絶好の撮影チャンス
- 下川岸地区での巡行は2025年限定の見逃せない見どころ
- 御旅所は神事の中心であり、山車整列会場とは別なので混同に注意